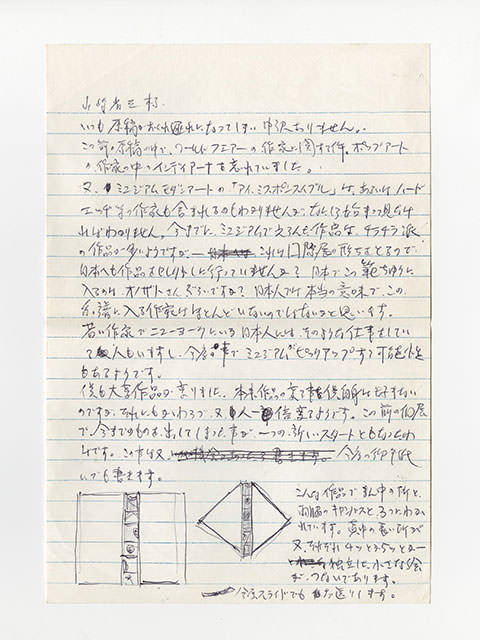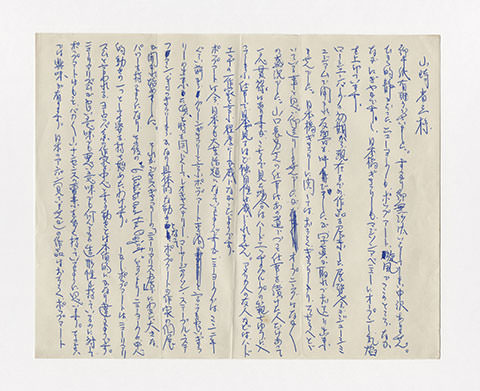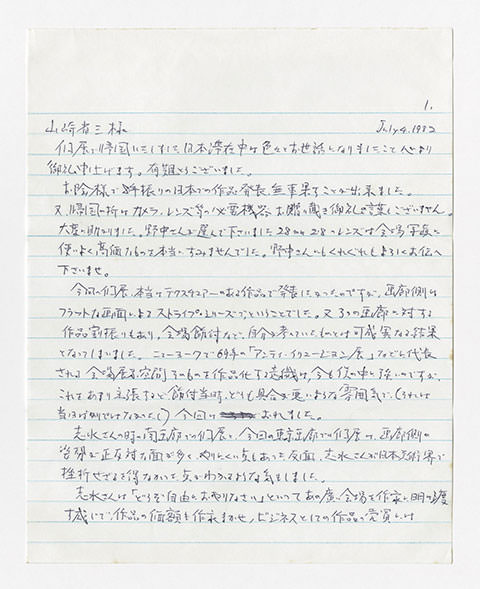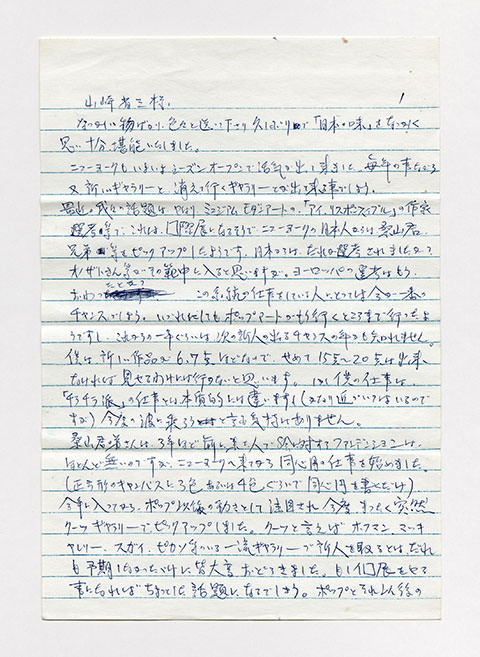Dec. 12. 1982
1982.12.12
山崎省三様
個展帰国の折は多々お力添えいたゞきましたこと、心より感謝いたしております。有難とうございました。山崎さんより頂きましたお手紙と僕の手紙がちょうどアラスカあたりですれちがったようで、そのまゝの御無沙汰お許し下さいませ。
芸新の編集部の仕事は続けられるとのお便り、なにかほっといたしました。日本で、ニューヨークで、お会いする方々も 皆そのことをのぞんでいらっしゃるようでした。
文章を書くなど思いもよらなかった僕が、良いか悪いかはともかくとして、文章を書くようになったのは61年以来のワールド・スナップ故であって、山崎さんとの出会なしにはこのことは考へられません。ですから山崎さんが芸新から引かれるようなことがもしあると、僕もなんとなく文章を書かなくなるかな? といった気もして来るのです。お陰様で貴重なニューヨーク美術の資料が十分手元にあるのですから、一つ本を書くべきだと、そのことが いつも頭の中心にあるのですが、やはり、そうとう自分をいためつけないと書けないような気もして なかなかスタート台につけません。先日 すし幸でお話しいたしました時、500枚ぐらいとおっしゃいましたが400字500枚ですね? どうしても来年はスタートしなければと思っています。
ニューヨーク美術界この年末もヨーロッパ系作家が活発な発表をおこなっています。伊藤さん、岡部さんのパリ通信が芸新に出だしてから、それは、我々にも大変に役立ちます。ニューヨークとヨーロッパの美術界は筒抜けのようでいながら、しのぎをけずるような力関係の駆け引きがあり、パリ通信とニューヨークの動向を合わせて見ると、成る程とそのからくりが立体的に読めて来て面白いのです。アメリカのシュナーベルやサールはアメリカの尖兵として ニューヨークよりはむしろ ヨーロッパの評価獲得に賭けているように見られるふしもあり、ベルリンで現在開かれている”Zeitgeist”展のような、この分野を総括的に示すような企画は ニューヨークではまったく見られません。ニューヨークは 現在も現代美術の国際的マーケットの中心という点では変りありませんので、ヨーロッパ系のこれらの作家達の作品発表は盛んですが、この動向自身は、ドイツ、イタリア等を中心としたヨーロッパ勢が仕掛人ではないかという気もします。ドイツ作家を集中的に発表するソナベンドは フランス系の画廊で レオ・キャステリイの別れた奥さんで、現在同じビルの2階と3階で、キャステリイとソナベンド、その息子の三人が上ったり下ったり 一家のようなものですし、同ビルの一階がメアリー・ブーン・ギャラリーです。イタリア作家をあつかっているのはローマのスピローネ・ギャラリーのニューヨーク・ブランチで、キャステリイの作家の多くがこの画廊と関連しています。この動向は実際には ヨーロッパと関係の深い4、5軒の限られた画廊のサークルが中心となって展開されているのですが、それらの画廊が ニューヨークの強力画廊であることゝ、ジャーナリズム(大衆雑誌など)が大々的にとり上げることが、この動向の印象を強くし またポピュラーにさせているようです。このことで不毛と停滞といわれながら 60年代美術以後のアメリカ独自の現代美術のありかたを模索して来た70年代アートの苦い10年が、急に中に浮いた感じとなりました。
アメリカの若い世代の人達は、この新表現の動向に夢中になる一方、大くのアメリカの作家達は ゲーッといった感じでシュナーベルを見ている面もあるのですが それは、彼の作品が根本的には抽象表現主義からラウシェンバークに至る転機をこえるものではない、といった受けとりかたがあるからだと思います。シュナーベルは51年生れ、ポップアート台頭の時はまだ11才だったわけで、60年代後半以後に自我を形成した作家ということになります。抽象表現主義末期をニューヨークで体験し、制作もした僕の世代は、その表現過多を否定して現在のような仕事をしているのです。一方 抽象表現主義が倒壊して10年、ミニマルアート全盛の時代から出発した新世代の彼等が、エモーショナルな表現に新鮮さを感じることは良くわかります。彼らの仕事を見ていると 世代の違いということをまざまざと感じさせられるのです。戦争体験を口にする昭和一桁生れと 昭和25年以後生れの若い世代の人達との違いといったようなことかも知れません。新たな動向ですから「ニュー」という字がついて、ニュー・ペインティング、ニュー・イメージ等といわれますが、これらの動向は決して前衛的なものではなく、むしろかなり保守的な姿勢を示すものだと思います。その点で自国の過去の美術史や古い逸話、キリコ等とのきずなも示すイタリアの作家達や、東西に引き裂かれたドイツの戦後の実状の中を生き、エコールド・パリとはことなるコンテクストの上に成り立つドイツ表現主義の伝統をふまえたドイツ作家達の作品には、帰るべき場に必然性が感じられるように思えます。
新表現の作家達は、ヘタクソ的ななぐりがきをやりますが、彼等はそれぞれ大変な技巧達者で、注意深く彼等の作品を見れば、並々ならぬ力量のもちぬしであることがわかります。シュナーベルも並とは違う希な画家としての資質に恵まれた作家ですが、先シーズン・オープンのグループ展に発表した大作以後は、ろくな作品にめぐりあえません。(写眞をとるときれいに見えるのですが) シュナーベルという作家自身を支える根がどこにあるのか? 歴史の浅いアメリカの中で アメリカという自国の独自性をさぐって来たのは実らなかった70年代の作家達であり、(シャピロは70年代の一つの結実として貴重な作家だと思います) 彼等は抽象表現主義や、ラウシェンバーグの繰り返しをやるというわけにはゆかなかったのです。シュナーベルはラウシェンバーグよりは病的だという点で、より今的であるかもしれず、より大規模な画面を一気に構築する力量は並み外れています。彼の作品には自信過多といったものを感じさせますが、力量と憑きとに賭けているかのようなシュナーベルの作品は、その憑きが落ちたら 泉が涸れるように全部崩れてしまうのではないかといった危殆を感じさせます。まさに死への瞑想であるかもしれません。
又だらだらと、とりとめもない事を書いてしまいました。他人はどうであれ、僕は、僕のやりかたでやって行きます。
どこか狂ってしまったようなニューヨークの陽気は、寒くなりかけては、又初春を思わせるような暖かさが戻って来たりします。
またゝく間に月日が流れ去り、もう後2週間で新年です。83年がより良き年でありますよう、皆様の御発展、御健勝を心より祈っております。
では新年も又何卒よろしくお願い申し上げます。又、お世話になりましたこと重ねて御礼申し上げます。有難とうございました。敬具
近藤竜男
美代子






Tag
Related Item